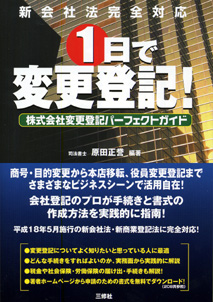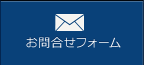2006年12月08日
株主総会議事録への押印の有無
5月の新会社法施行でのドタバタ騒ぎから7ヶ月が過ぎ、当時の混乱が多少懐かしく思える余裕が出てきた今日この頃、
商事法務より11月30日臨時増刊号「株主総会白書」が送られてきました。
6月の定時総会の準備をしていた頃、関与先以外の他社の株主総会対応の動向が気になっていましたが、
やっと各社のアンケートが集計されたようです。
会社法か商法のどちらで開催をしたか(旧商法が65.4%)
などのアンケートに始まり、司法書士の関心の高い分野でも色々なアンケート結果が出ております。購入されてない方はこの機会に是非。
ご存知のように会社法では株主総会議事録には、総会議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名を記載する必要があります。
これに関しては、当初の予想通り、代表取締役または総務担当取締役がその大部分を占めていました。
議事録の完成まで数日を要した関与先もありましたが、商事法務の集計では、総会当日に議事録の作成が終わった企業が25.4%
と最も多かったようです。
たぶん司法書士が最も関心の高い質問が「株主総会議事録への押印の有無」でしょう。
会社法での株主総会議事録には出席取締役の記名押印がいらなくなりました。議案を印刷しただけの
「どこにもハンコが押されていない株主総会議事録でもOK」というのに違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
私の関与先には、「今回は他社動向を見守りましょう。」と従来通り「押印した議事録」の作成をお勧めしていたのですが、
実際のアンケートの結果はどうなんでしょう?
資本金5億未満の会社では、議事録の押印を行った企業は83.3%と想定の範囲内(古(笑)。)ですが、
大企業ともなるとちょっと違うようです。
さて問題。
資本金1000億円超の企業のうち、株主総会議事録に押印を行ったのは、
全体の何%?
A 32.2%
B 47.4%
C 51.8%
D 70.9%
「議事録の真正担保と手間いらず」どちらを優先したんでしょう?
正解は→A