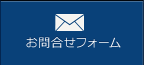2005年11月01日
司法書士試験合格者の皆さんへ
今日平成17年の司法書士本試験の最終合格者の発表がありました。(法務省の詳細内容のあるHPはこちら)口述試験では、落ちないと思っていても今日の結果が出るまで不安だった方もいらっしゃると思いますが、まずは、合格おめでとうございます。まだまだ心配な方は官報を買って自分の名前を確認して下さい(笑)。
法務省の詳細によると、
出願者数(A) 31,061名
合格者数(B) 883名(男636名・72.0% 女247名・28.0%)
合格率(B/A) 2.8%
出願者・合格者・合格率ともに例年よりアップしています。司法書士が883名増えることになります。800名弱・合格率2.5%ぐらいかなあと思ってましたが、思ったより多かったですね。883名のライバルの誕生です。
試験に受かった方は、中央・ブロック・単位会・特別研修(場合によっては配属研修)が待っています。新不動産登記法の実務を学ぶのもこれからでしょうし、現行の商法で合格された訳ですから、新会社法の勉強もこれからです。未知の世界だと思いますが、要件事実論を学び、弁護士やチューターにいじめられるのもこれからです(笑)。その他、裁判実務・クレサラ・成年後見と学ぶものは果てしないと思います。
「試験に合格したんだから勘弁してよ!」という声が聞こえてきそうですが、あなた方は、我々の立派なライバルです。正直合格しただけでは、我々との勝負になりませんが、これから日々努力され、それぞれの分野で活躍されることを祈っています。(私のマーケットをあんまり荒らさないでね。という気持ちもありますが(笑)。)
P.S.
1年前に退職して、受験勉強に専念していたスタッフが、試験に合格して、今日から職場に戻って来ました。彼女を入れて、司法書士ライセンス3名体制となりましたので、今後は、より高い品質のサービスが提供できるのではないかと思っています。どしどし質問して鍛えてあげて下さい。宜しくお願いします(笑)。