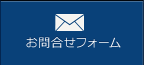2004年01月20日
可哀想な後見人
成年後見というと自己の判断能力の低下した(ボケた)方々をサポートする制度なんですが、可哀想なケースもあります。
何らかの事情で、第三者が自己の判断能力の低下した方と契約したい場合は、そのままそのボケた方と契約を締結しても意味がありません。そのボケた方の代わりに契約を締結できる後見人と契約することになります。契約したいのにこの後見人がいない場合は、後見人選任の申立てをすることになります。後見人には親族のだれかが選任される場合もありますし、我々のような職業後見人が就任する場合もあります。
徐々にこの成年後見の制度が広まりつつはありますが、まだまだ一般の方には馴染みのない制度です。あまりこの制度を理解されぬまま安易に後見人に就任してしまうと、裁判所から連絡がきたりしてビックリする事が多いようです。結構手間がかかることもいっぱいあります。
親族が後見人になる場合に、事前に「後見人の仕事、仕組み」を理解してもらうためにリーガル・サポートでは後見人養成講座を開いたりしています。これらの講座からこの制度を理解し、後見人に就任すればあまり戸惑うこともないと思います。
しかし、第三者がボケた方と契約したいためだけに、この制度を利用し、成年後見の仕組みも理解していない親族を後見人に就任させて、契約を締結して「後は知らんプリ」では、日々介護に追われる親族からしてみると負担が大きすぎます。介護の負担の重い親族が、裁判所に振りまわされる状態は本来の制度趣旨から大きく外れてます。ボケたお金持ちの回りには、いい人だけが集まることは少ないようです。(今日はちょっと真面目すぎましたね。)