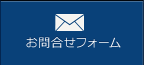2003年06月04日
キリマンジャロ−その9
でもここまで来たら行くしかないですよね。カップのふちをしばらく歩くと太陽が昇ってきました。真っ暗だったあたりが急に明るくなりました。回りの風景はクールミントガムの包装紙のようです。(イメージ湧きますか?)あちこちに青白い巨大な氷の壁があります。
赤道直下なのに南極のような景色です。途中で一度足を滑らせました。大きな雪の塊がすり鉢の中を転げていきます。後で聞いたところによると、他のグループは私が落ちたと思っていたそうです。くわばら、くわばら。半歩半歩あるくのが苦しく、気のせいか手にはめたグローブや上着が重く感じられます。よっぽどグローブと上着を捨てようかと思いました。今考えるとどうにかしてますね(笑)。
キボハット出発して9時間ぐらい経過したでしょうか。とうとうウフルピーク(5,895m)に到達しました。そこには小さな看板があり「Highest point in Africa」と書いてありました。冒険野郎たちは待ちくたびれた様子でした。ベテランのシェルパはこの頂上でなんと煙草を吸って待っていました。(こっちは酸素がないっていうのに信じられません。)育った環境でスゴイですね。
あとはひたすら降りるだけです。気分もどんどん良くなるはずです。
冒険野郎はこの高度なのに走って降りて行きました。結局イギリス人の冒険野郎見習と降りることになりました。登りと違って下りは楽です。しかし私の体調が良くないので、他の人たちと離されてしまいました。そのうち、他のグループをすっかり見失ってしまいました。3時間も降りればもとのキャンプ地に着くはずです。ところが4時間たっても5時間たってもキャンプ地に到着しません。どうやら降りるルートを間違ったみたいです。
イギリス人の冒険野郎見習とは口論が続きます。人間って極限では本性でますね。相手をいたわる気持ちが無くなってきます。
冷静に考えても考えなくても我々は遭難したみたいです。