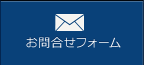2003年04月28日
特別研修いよいよはじまる!
いよいよ始まった特別研修に昨日、一昨日と出席してきました。研修費75000円だった分、ライブ中継等設備にだいぶお金をかけてます。休み時間にはなぜか「サザンオールスターズ」の曲が流れてました(笑)。研修の内容はインターネットで公開しないようにとの御達しがありましたので、内容は割愛させて頂きます。東京の会場(日司連ホール)では2日間で遅刻者0でした。みんな気合が入ってるようです。1講義ごとに出席の確認があり、早退者がいないように見張りまでいて、がんじがらめの2日間でした。ずっと座りっぱなしでエコノミー症候群になりそうです。
今日、明日、明後日もその後も研修。課題もたっぷり出ています。安息の日はいつ訪れるのでしょうか??
PS 今日月曜日というかんじが全くしません。(体内時計的には金曜日(笑)。)
【登記一口メモ】というより訴訟一口メモです。平成15年4月より司法書士法の改正があり、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権が付与されます。今回の特別研修はこの法務大臣の認定を得るためのものです。認定がでると訴額90万円(改正されて140万円に引き上げられそうですが)までの訴訟代理人となれます